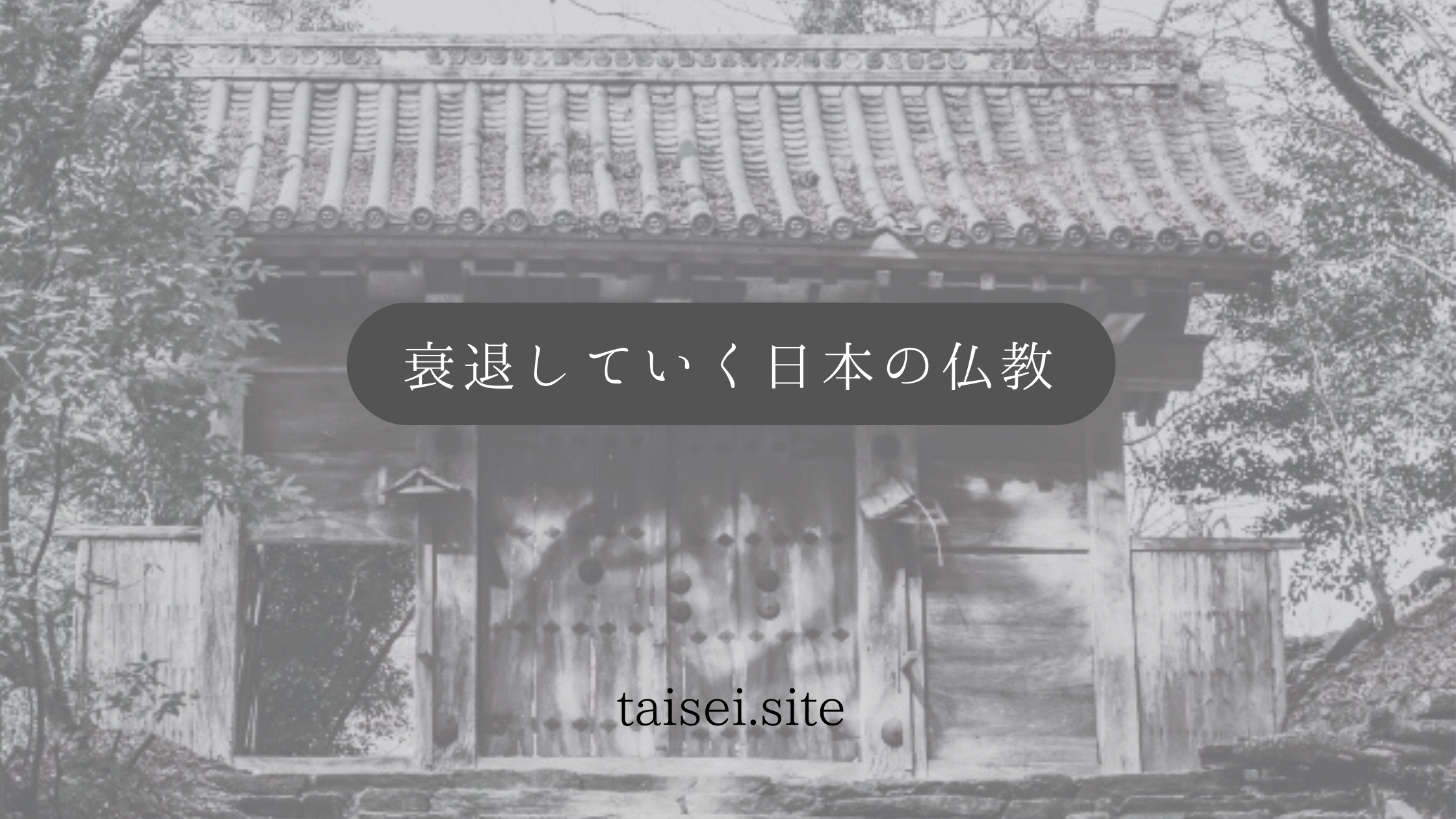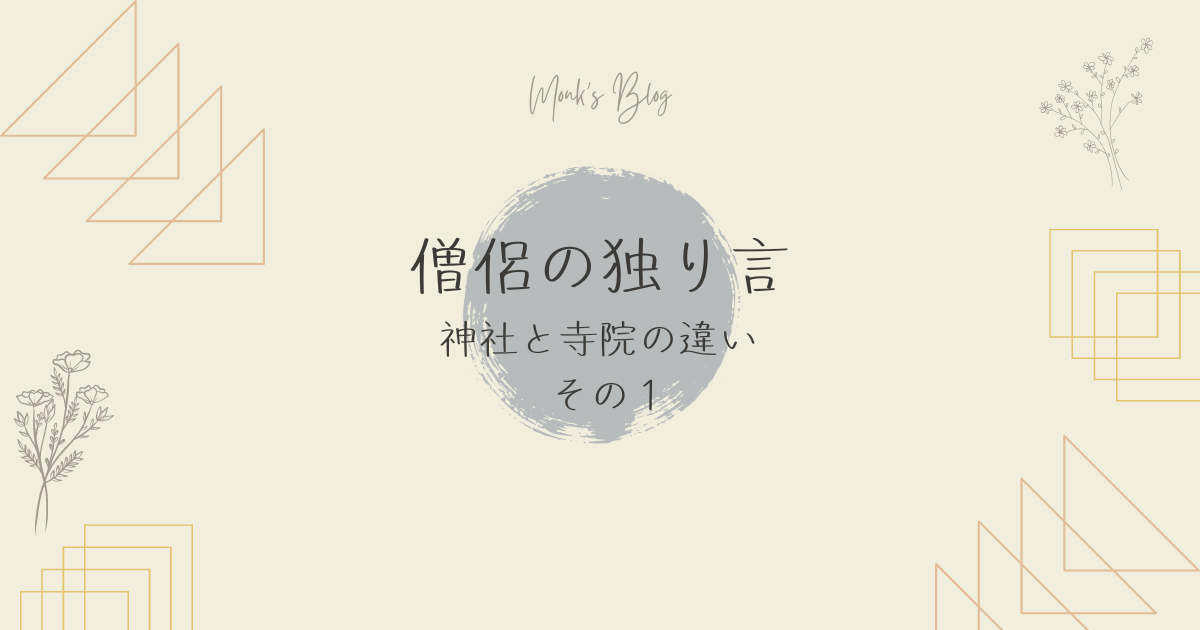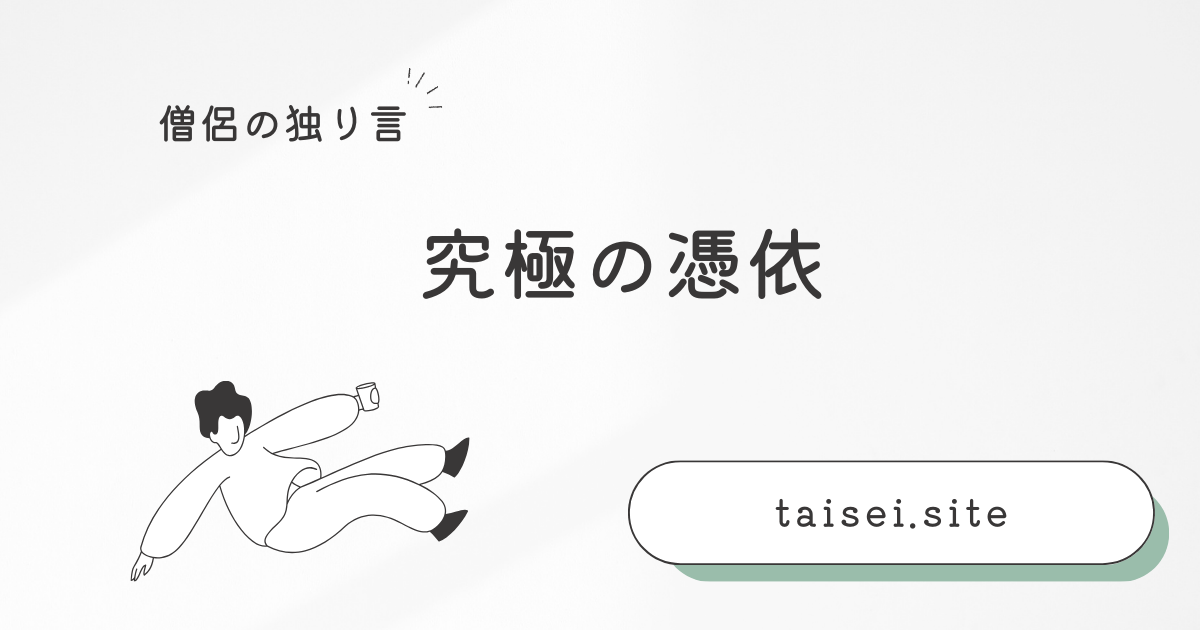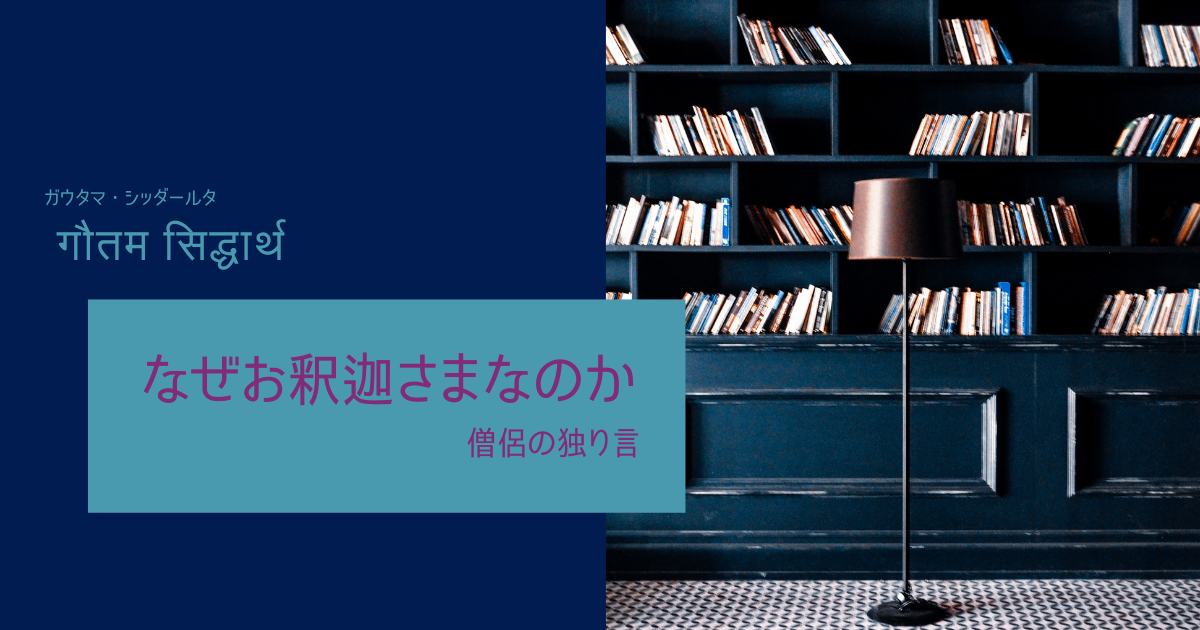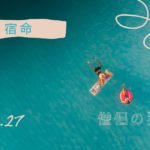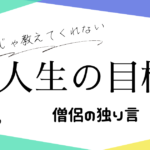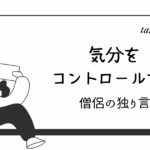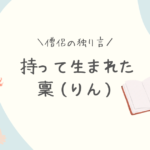現代仏教への危機感
日本の仏教は、鎌倉時代に親鸞・日蓮上人など開祖の教えとして民衆に広まったことに端を発します。日本における宗教界の一大革命と言えるでしょう。
時代を経るにつれて、その姿は変貌していき江戸時代からはじまった檀家制度によって、寺院の役割は限定的なものになっていきました。
檀家制度に胡坐をかいてしまった寺院は、本来の役割をおざなりにしてしまい、宗教的・社会的地位の凋落に歯止めが止まらなくなっています。
その傾向は統計にも表れていて、かつてコンビニよりも多いとされた寺院は、潜在的な消滅数を含めてその数は急速に減少しています。人々が寺院ばかりか、仏教そのものの意味について疑問を呈し始めたのです。
ここでの問題点は、本来のお釈迦さまの教えを表面的にしてしまったこと。
日本仏教衰退の中、多くの邪教による誤った信仰が民衆のこころを蝕み、五濁悪世を助長してしまったことは残念でなりません。一方で、仏教の意味が薄れていった証左ではないかとも思われます。
後世のために、お釈迦さまの教えをそのまま後世に伝えていきたい。わたしは、現代社会における[お釈迦さまの教え->仏教]そのものの衰退に対して危惧しています。
お釈迦様の教えを初期に立ち戻って、人々の人生の指針として取り戻したい。
植物は太陽に向かって自らを伸ばしていきます。時折、道端やベンチの脇にも太陽を求めて異様に曲がった植物を見かけることがあります。このように植物は、自らの栄養になり、育ててくれる太陽に対してまっすぐと伸びていくのです。
ところが、人はどうでしょう。植物と違って人は幸福と平和を求めながらも、往々にして固執しがちな自己観念が邪魔をして、自分の基盤を自らの手で壊してしまうことさえあります。
植物にとっての太陽が人にとっての幸せとするならば、人はその幸せへ率直に自分を伸ばすことができないのです。
戦争・家庭崩壊・自然破壊・ハラスメントや虐待など、人は自分自身ばかりか他者さえも害するような暗闇へと向かっていってしまう矛盾をはらんだ存在なのです。
人は過ちを繰り返す
人生の目的とは
自分の生まてきた理由を自身に問う
五濁悪世では、自分を見失わせるようなシステムが当たり前のように機能しています。人々はあたかもロボットのように、情報に流されて欲望の炎に焼かれながら一生を終えてしまっているかのようです。
このブログは、お釈迦さまの教えを伝えていこうなどと、だいそれた考えに立っているわけではありません。ただ、欲望の炎に包まれた人々に、目に見えない世界を垣間見ることで、まずは現状に気が付いてほしいだけなのです。
わたしは、福岡は糸島という風光明媚な場所に住んでいます。この拙いブログは、この糸島からその悲願のための小さな歩みだと信じています。