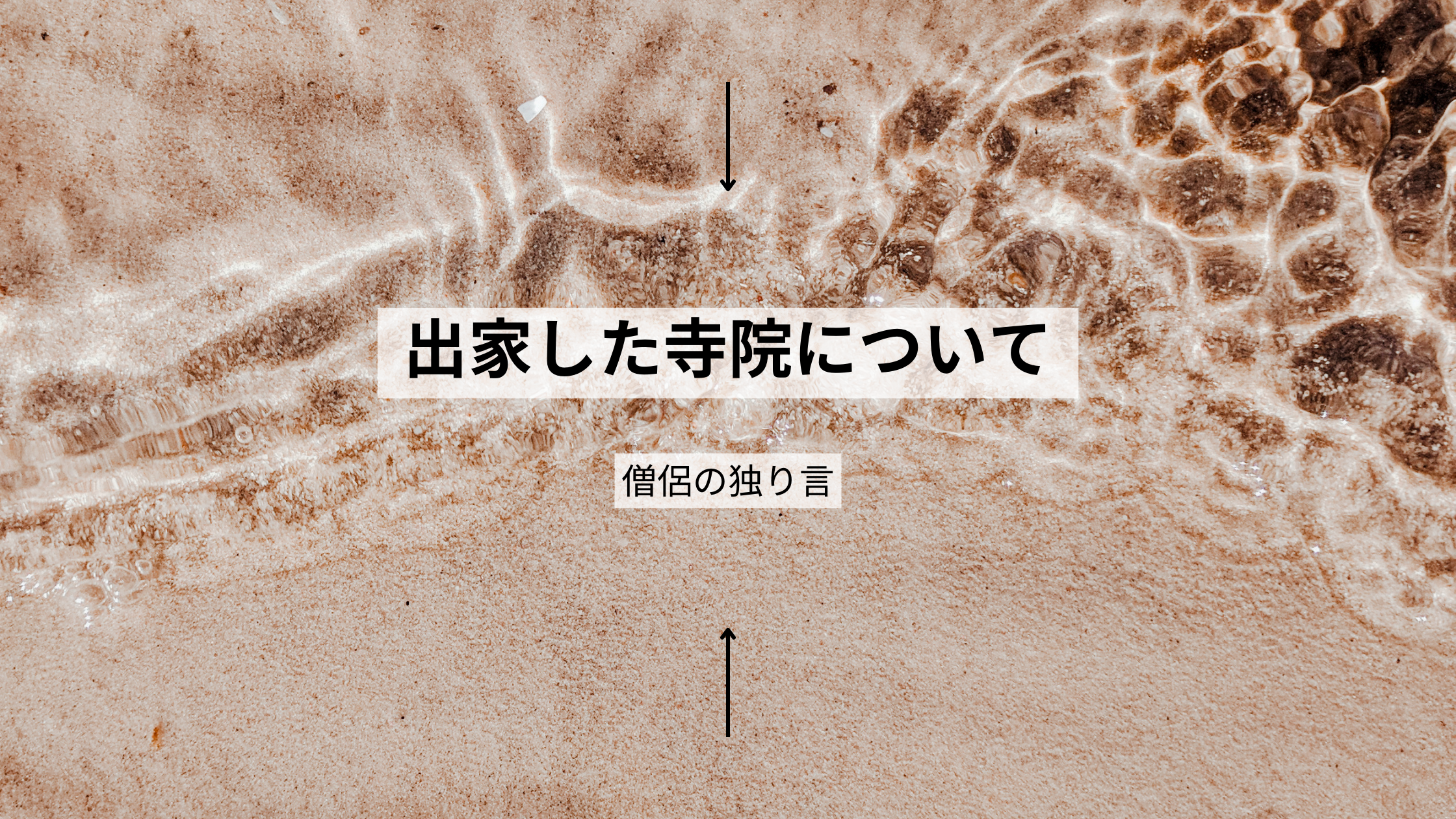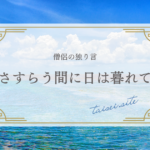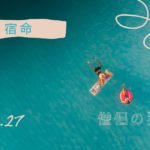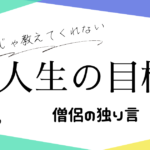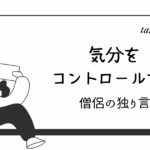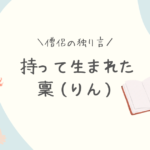注意)以下の記事には、生死に関わる微妙な内容が含まれています。
特に気の弱い方や神経質な方、霊感の強い方で修行されていないは、
読まないようお願いいたします。
寺院のあるところ
出家した寺院は、数百年前、激しい戦いによって数千人もの亡くなった古戦場に建っています。巻き沿いになったて亡くなった民衆まであわせると一万人を超えるかもしれません。
戦乱の当時は手厚く葬ることも難しく、屍の跡が累々と続いていたことでしょう。
この場所に縁を頂き、半世紀ほど前に深い山を切り開いて寺院は建てられましたが、敷地の外側には、いつだれが建てたともしれない五輪塔1が、まだあちこちにあって、大雨等続けば、その痕跡が敷地内に流れ落ちてくるほどです。
なお、寺院建設中においても、目に見えない世界を織り交ぜて、筆舌に尽くせないほどたくさんのことが起こりました。
供養塔
建てられた当初は、そこら中に武士の魂が闊歩していました。(魂という言葉は不適切と思われますが、一般的に通用する言葉でもありますのであえて使用しています。)
当時の僧侶たちが厨房で食事をしていると、血だらけの武士たちが、窓に張り付いて覗いていたそうです。わたしが出家した頃には、供養も行き届いてきて、だいぶ落ち着いてはきていました。それでも、わたしと同じ年に出家した方が夜中ふと目が覚めると、甲冑を着た武士が添い寝をしていたそうです。
寺院の敷地内には、寺院が建立した大きな供養塔が数か所あります。出家した当初は朝の4時過ぎに起きて、それらの供養塔と納骨堂と合わせて、お茶と水の交換と読経をして回りました。まだ暗く、見通しの悪い山道を、お茶と水を入れた大きなヤカンを両手に持っておよそ一時間。
わたしが出家した頃には、霊が出現する場所は、大体決まっていました。でも、暗闇の中、わたしは霊に出会うより、むしろイノシシと鉢合わせする方が怖かった記憶があります。
武士の霊たちについて
武士の格好をして、うろついている霊というのは、亡くなって数百年が経過しても、まだ戦争が続いていると信じているものたちです。それらの(元)人たちは、自分の意思で供養塔に入り、供養を受けることもできる(た)のです。
しかし、供養塔の中には管理人のような方がいらして、そこに入るためには、少なくともこの世との未練を断ち切り、その管理人の許可を得なければなりません。白装束を着、この世の未練のない意志を示してはじめて供養塔に入ることを許されるのです。
きっと、これを読んでいらっしゃる方のほとんどは、亡くなれば簡単にあの世に行けると思っている方がほとんどではないでしょうか。ちなみに、僧侶の出家得度式というのは、この世の未練を捨てて生きたまま葬式を挙げることです。
ですので、僧侶の名というのは、亡くなって付けられる戒名に当たります。
武士たちの未練
迷い続ける武士たちは、主君への忠誠心か、それとも武士としての誇りや意地が邪魔しているのでしょうか。数百年の間、ひたすら戦い続けています。これも、人のこころの癖のひとつと言えるでしょう。
中世の武士と言えば、仲間と信じ切っていた親族からも、背後から襲われてしまうような特殊な世界に生きていた人たちです。真剣を振り回し、血を血で洗うような戦国時代は、平和な現代とは違い、そのメンタルは極限状態だったことでしょう。
そこで、培われたこころの癖は、数百年の時を経ても、そうそう解(ほど)けないことは容易に想像できます。
そんな戦国の世に身をおきながら供養塔に入ることができたというのは、現代よりも強いこころを持った人々が、多かったこともあるのかもしれません。むしろ、欲望にまみれ、この世の未練だけは強いこころの弱い現代人の方が、戦国の武士よりもあの世に至るまで時間を要するのかもしれません。
おわりに
戦い続けることで、こころ休まり、幸せになれるはずもないのに、固執した信念に囚われている人間というのは、ほんとうに悲しい生き物だと痛感してしまいます。
今回は、わたしが出家した寺院がある土地の事情についてざっくりお話ししてみました。今でいう所の事故物件ですが、たまたまそこに建てたのではなく、進んでそこに建てたことが単なる事故物件とは大きく違う所です。
語るべきお話しはまだまだ尽きませんが、さらに長くなってしまいそうなので、今回はこの辺で終わりにいたします。
次回は、目に見えない世界について、少し掘り下げてみたいと思います。
- 亡くなった主に武士の供養のために石を重ねて作られた小さな塔 ↩︎